【セルフレジ 行きつけ失う高齢者】デジタル化の波が奪う日常の居場所
冒頭文
近年、スーパーや飲食店で急速に広がるセルフレジやタブレット注文。効率化や人件費削減を目的に導入が進む一方で、高齢者にとっては“行きつけの店を失うきっかけ”にもなっています。スマホ操作が前提となる店舗では、ガラケーしか使えない人や視力が低下した人にとって、注文や会計が困難に。「昔から通っていた店なのに、もう行けなくなった」という声が各地で聞かれています。
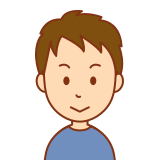
セルフレジ 行きつけ失う高齢者
結論
セルフレジの普及は、利便性の向上と引き換えに、高齢者の居場所を奪う結果にもつながっています。操作に不慣れな高齢者は、レジ前で戸惑い、後ろの列に気を使いながら焦ってしまうことも多く、買い物の楽しみが不安に変わる瞬間を迎えています。紙のメニュー廃止やQRコード注文など、デジタル化が進む店舗では、長年通っていた“行きつけ”を諦めざるを得ないケースも増加。社会参加の場が失われることは、孤立や不安の要因にもなり得ます。
理由
この問題の背景には、デジタル化の急速な進行と、それに伴う“排除の副作用”があります。若年層には便利なセルフレジも、高齢者には心理的な壁となり、操作に困った際に声をかけづらい環境が孤立感を生みます。また、タッチパネルの反応や文字の視認性など、身体的な負担も大きく、店舗側の配慮が不足しているケースも見受けられます。買い物や外食は単なる消費行動ではなく、地域とのつながりや社会参加の場であることを忘れてはなりません。
まとめ
セルフレジの導入は、店舗運営の効率化に貢献する一方で、高齢者にとっては日常の居場所を失う要因にもなっています。スマホ操作が前提となる社会の中で、誰もが安心して利用できる環境づくりが求められています。優先レジの設置や有人対応の継続、操作サポートの充実など、店舗側の工夫が不可欠です。高齢者が安心して買い物や外食を楽しめる社会こそが、真の意味での“便利”を実現する鍵となるでしょう。
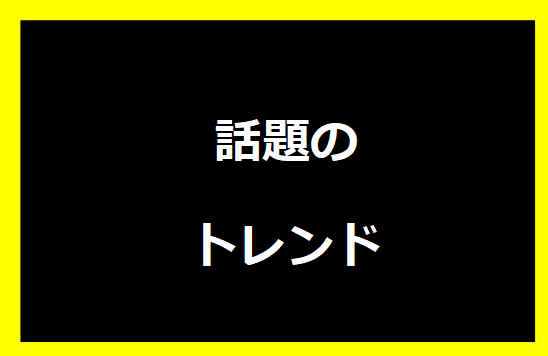
コメント